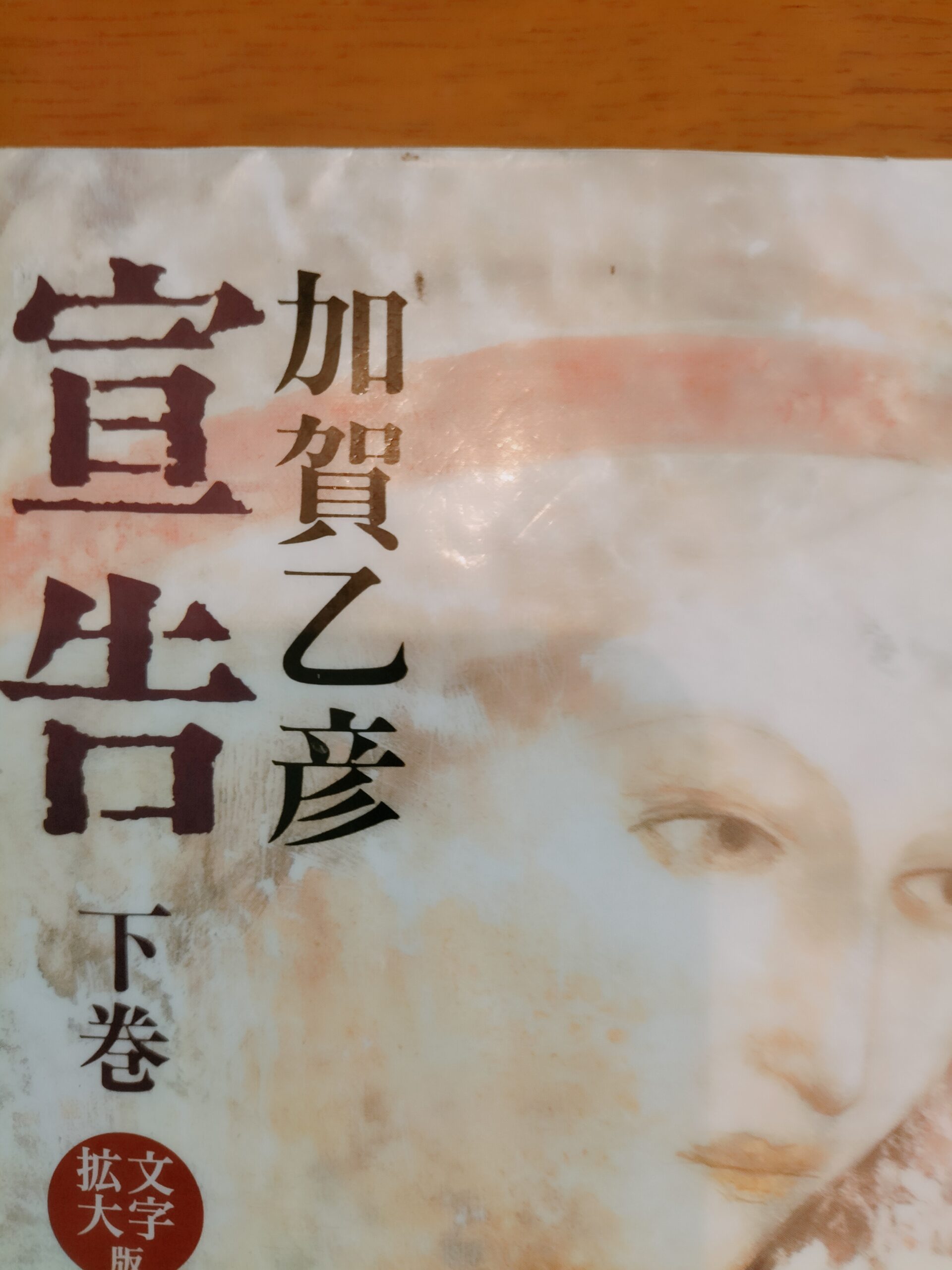『宣告』(加賀乙彦著)
訃報に接し、初めて手に取った。加賀乙彦さん著『宣告』(上中下巻、1979年、新潮文庫)。交流があった実在の死刑囚をモデルに拘置所医官を務めた精神科医・小説家が書いた長編小説だ。テーマの重さとリアリティにたじろぎながらやっと読み終えた。いや、正確に言うと、最終盤、主人公の楠本他家雄が刑を執行される部分については、正視することができなかった。
本書は「死刑反対」の書である。記者が正視できなかった部分は、淡々としかもこれでもかと絞首刑の細部と生身の人間の死を描写することで死刑の残酷さを告発する。読んでいて気分が悪くなった。
また、別の死刑囚が訴える次の言葉は、死刑が死刑以上の精神的拷問刑であること教える。
「こっちは、四年も五年もいつ殺されるかって毎日、そうだよ毎日苦しんで、(中略)。死刑の判決があってから長く生かしたほうが人道的だとでもいうのかい。こっちは、死を待つことが一番苦しい、そうだよ死ぬことよりもっと苦しいのによ、この苦しみを毎日毎日続けさせるのが人道的だっていうのかい」
本書では、この精神的拷問刑に耐えられず、拘禁ノイローゼになる死刑囚が多く描かれる。死刑の残酷さも拷問刑の側面も少し考えれば思い至ることだが、目を背けたくなる現実でもある。本書はそれをあえて言語化することで、読者が死刑制度を少しでも具体的に考えられるよう補助線を引いてくれた。想像してほしい、と語りかけている。死刑を考えるうえで必読の書である。
「科学と文学は別々のものではなく、1つのものの2つの側面である」(英生物学者トーマス・ハックスレー)。科学者であり文学者だった加賀さんのご冥福をお祈りする。(2023.02.26)