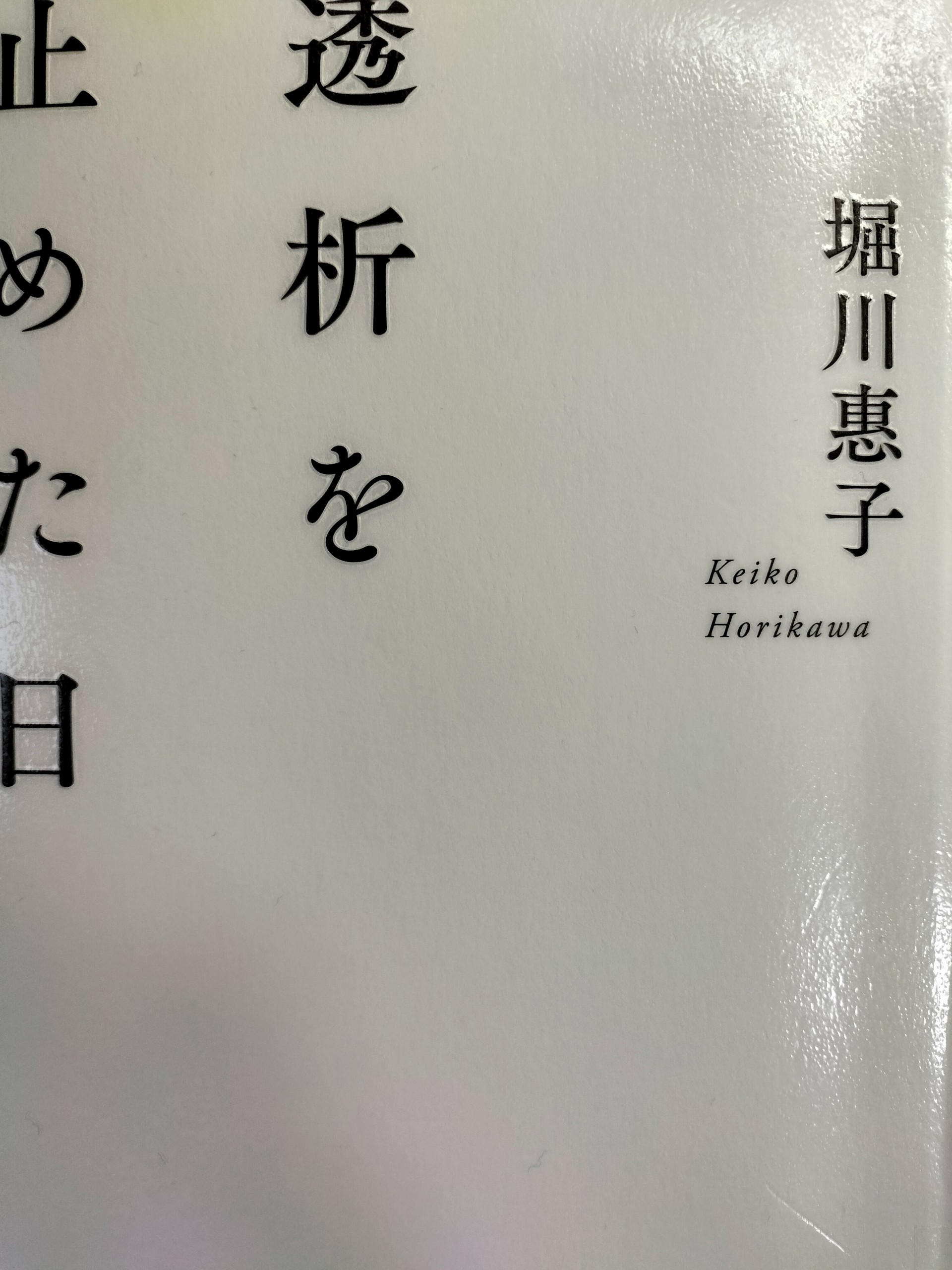『透析を止めた日』(堀川惠子著)
これまでの著書を読んで、ライターとしての堀川惠子さんを尊敬していた。だが、理解が浅かった。ライターとしての矜持、覚悟、他者への心遣い…。『透析を止めた日』(2024年11月、講談社)の全てに圧倒された。
記者は高校生の頃にネフローゼという腎疾患を罹い入院していた。だから、腎移植や人工透析は人ごとではない。再発への恐怖心はまだある。そこに堀川さんの著書。手に取らないわけにはいかない。
数々ノンフィクション賞を受賞した作品の中でも圧巻だった。第1部は、夫であるテレビプロデューサー林新さんの闘病とその介護、そして最後は透析を止め、亡くなるまでを綴った。記者も不勉強で知らなかったが、緩和ケアはがん患者だけのもので、透析患者の終末期には制度上適用されない。そのため林さんは〈人生最後の数日に人生最大の苦しみ〉を味わうことになる。機械に頼っていた排尿ができなくなる。水分も老廃物も毒も体に溜まる。高校生当時、体中に水が溜まりむくんだ恐怖がよみがえる。透析ができなくなる日が訪れることも記者は知らなかった。堀川さんの筆になる林さんの闘病の様子は凄絶だ。
堀川さんはその不条理を、愛する人を失う悲しみを、当時の記録と付き合わせながら、冷静に、時に感情的に記す。こんな記述がある。〈私たちの生きがい、人生の価値は、ゆっくり安楽に過ごすこととは一致してくれなかった〉〈取材者の目を持つ患者の家族として(中略)理由あって与えられた試練だったと考えざるを得ない〉
もし記者の家族が林さんの立場なら、とてもそんな風には考えられない。さらに、介護と並行してノンフィクション最高の賞を受賞するような作品を書いてしまう。まさに当代ナンバー1のノンフィクションライターだろう。家庭では片時も夫のそばをそばを離れず、いたわり続ける。スーパーマンでもある。本書は夫婦の愛情物語にもなっていて、心を揺さぶる。この業界、はちゃめちゃな人が多いのだが、堀川さんは家庭人としても真っ当な尊敬できる人だった。記者はその面でも失格であり、反省させられる。
透析患者の終末期について問題提起する第2部で、従来の血液透析ではなく、患者負担が小さいという腹膜透析を積極的に取り入れている医師が、堀川さんのインタビューにこう答えている。〈国会や学会のエラい人たちも、僕が話したようなことはとうに分かっているはずだけど、しがらみがあるのかな、動きは鈍いね〉
この本をきっかけに、終末期の透析患者の緩和ケア充実などを求める超党派の動きが出ている。透析患者の終末期をめぐる不条理は業界では常識だが、一般にはタブー視されていたという。一部の世界での常識は、世間ではニュースである。業界の常識を、患者やその家族の目線で「非常識だ」と著名なライターがまさに命懸けで告発した意味は大きい。堀川さんも本書の編集者も「この本を育てる」と言っている。日本の医療にとって大切な本である。ぜひ多くの人に読んでほしい。今年読んだベストだった。(2025.12.24 No.183)