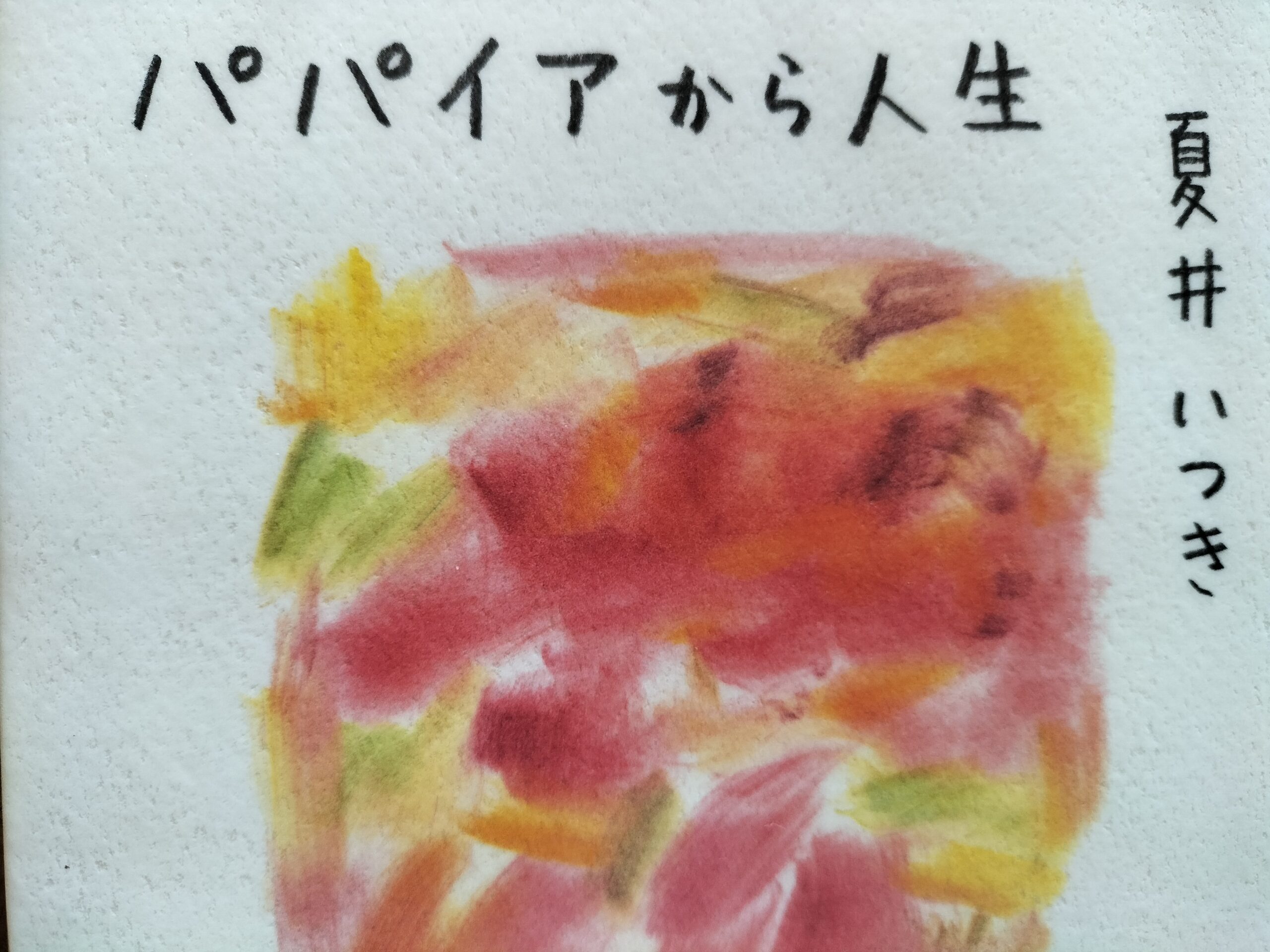『パパイアから人生』(夏井いつき著)
簡単そうで難しい。俳句のことだ。例えば季語にもなっている「すみれ」。漢字だと「菫」。読めない。旧仮名遣いで五七五の定型が崩れると、どこで切っていいか分からない句が散見される。ここで諦めてしまう人は多いと思う。
そんな人にお勧めなのが、テレビのバラエティ番組『プレバト‼』でお馴染みの俳人、夏井いつきさんの俳句にまつわるエッセイ集だ。意外とロジカルな文芸であることが分かる。知らない言葉も辞書さえあれば読み解ける。ネットで調べるのもありだ。ネガティブケイパビリティの足りない記者にはもってこいだ。
最近、『瓢箪から人生』『パパイアから人生』(小学館、25年6月)など、夏井さんの著書をまとめて数冊読んだ。それらが教えてくれるのは「解釈鑑賞は文藝」ということだ。例えば次の高校生の一句。
月涼し伽藍に蟹の道のある 小田健太
伽藍を東南アジアのものと解釈したときの著者の鑑賞はこうだ。
「その瞬間、私の鼻腔には、南国の甘やかな果実の香りが溢れてきた。(略)嗚呼、と心が震える。産卵という蟹たちの生命の儀式と、死を司る伽藍の静けさ。大地の熱を冷ますように、地上の森羅万象を慈しむように、月は涼やかにそこにある」
痺れた。元の句だけでは想像しえない奥行きのある世界が5感に訴えてくる。「批評するとは、他人の作品をダシに使って自己を語る事である」と語ったのは小林秀雄。夏井さんは鑑賞を通して元の句と一対の文芸を生み出している。俳句は優れた鑑賞があってなお輝きを増す文芸なのだろう。
それにしても韻文が書ける人の散文は上手い。夏井さんのエッセイは俳句の魅力を「俳句の種蒔き運動」による実体験をもとに伝えている。少しでも興味があれば、入門書として最適である。(2025.08.03 No.174)