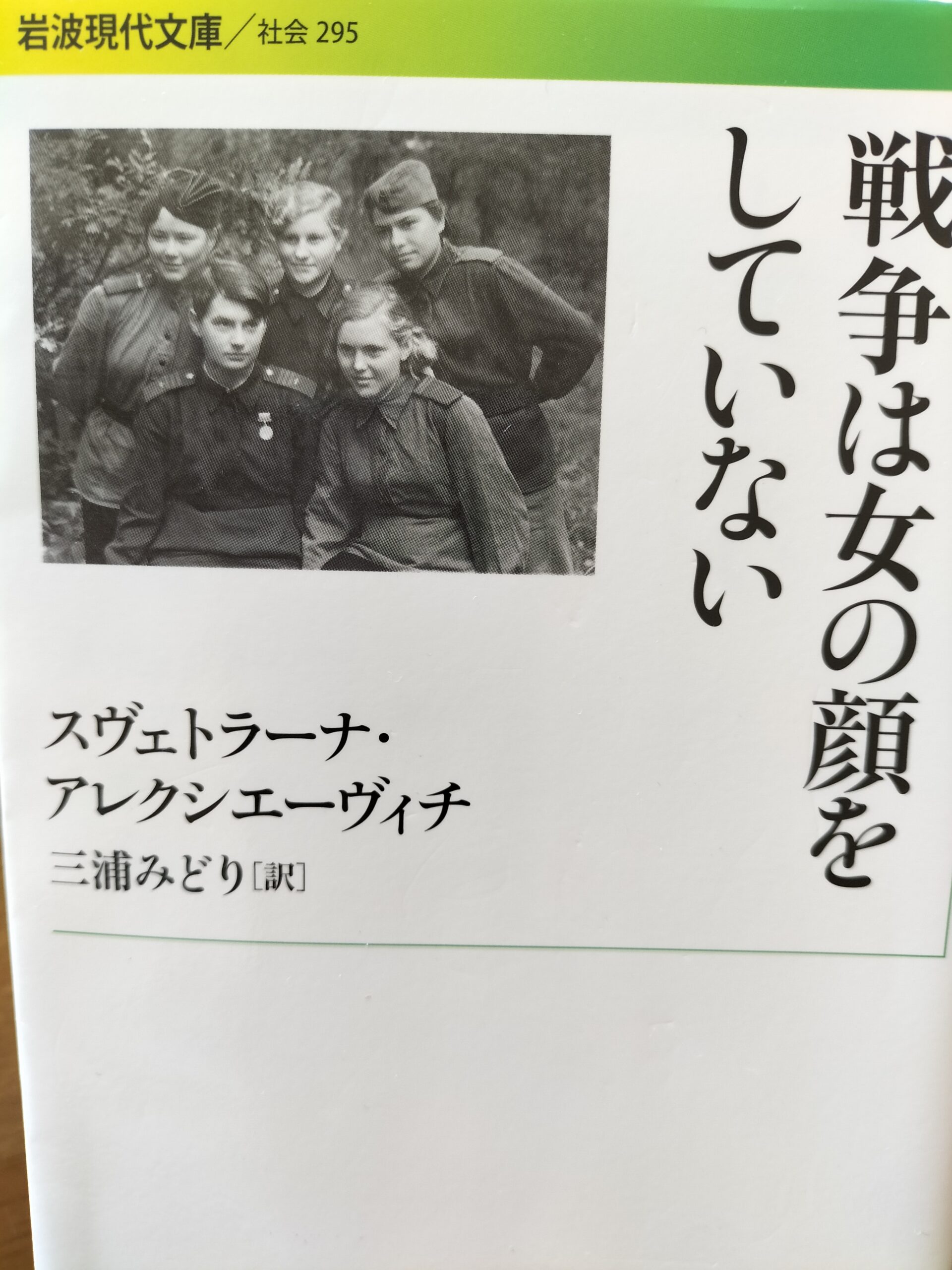『戦争は女の顔をしていない』アレクシエーヴィチ・スヴェトラーナ著
『同志少女よ、敵を撃て』逢坂冬馬著
これまでの自分の読書体験では、石牟礼道子著『苦海浄土―わが水俣病』(講談社文庫)に近いだろうか。感性豊かな詩人であり、目線を低くしたジャーナリストである女性の作品。アレクシエーヴィチ・スヴェトラーナ著『戦争は女の顔をしていない』(岩波文庫)を読んだ。事実が想像力を上回ったと感じたもう一冊だ。今年の本屋大賞を受賞した逢坂冬馬著『同志少女よ、敵を撃て』(早川書房)の種本の一つだという。もちろん、『同志…』も楽しんだのだが、それ以上に当事者でなければ語れないエピソードの連続に圧倒された。
世界史の教科書に単語だけ載っていたかな?という程度の記憶しかない独ソ戦争がテーマ。多くの日本人にとっても遠い世界の話だと思う。だが、響いた。『戦争は…』は淡々と、しかし、これでもか、これでもかと当事者の言葉を投げつけることによって、戦争の持つ悲惨な実態の普遍性を浮き彫りにしたからだ。戦略や兵器、武勇伝は出てこない。銃後の守りに徹した女性ではなく、看護婦としてのみならず兵士として武器を取って戦った女性ら500人以上の従軍女性の証言集だ。
『戦争は…』は、著者のジャーナリスト、スヴェトラーナさんが隠されてきたソ連従軍女性たちの声を発掘し、インタビューに至る経緯から始まり、インタビュイーの一人語りへと入っていく形をとっている。それが、不思議なことに自分で取材している気分にさせる。一人語りでは、独ソ戦の最前線に放り込まれたように情景や音や匂いを感じる。スヴェトラーナさんが記している。
「わたしの見ている前で物語は『人間の顔を持つように』なる。感動的な語り手に出会う。彼女たちの人生には優れた古典的名作にも劣らぬページがある」
「私たち、まったく子供のうちに戦場に行ったんだからね。小娘で。戦争中に背が伸びたほど。母が計ってくれたけど十センチも伸びてたわ」(狙撃兵)、「人間は死んで行きながらも、やはり自分が死ぬということが信じられないんです」(看護師)…
『戦争は…』は優れた語り手により、「記録文学」から超一級の「戦争文学」に昇華した。ノンフィクションの力だ。